スティーブ・バノンを突き動かすものは何か(What Does Steve Bannon Want?)
2017年3月14日(火)12℃ くもり時々雨
114.827 ¥/$
トランプ個人の動向に対する世の中の関心も少々薄れてきたような気がする。一般論に逃げるのはやめよう。トランプ個人をいくらひっくり返しても、何も出てきそうにもないことがわかってきて、僕も少々飽きてきた。さすがに彼のリアリティショーもシーズン2を見る気はしない。しかしトランプ政権から逃げることは当面できそうにもない。
4年間持つにせよ、持たないにせよ、その動向と方向性から目を離すべきでないからだ。

トランプの薄さの裏側に、バノンという重さがある。インテリによって構成されるマスメディアも、さすがに、敵にしても似たモノを求めるのか、バノンに対する関心は高まる一方である。このあたりは、異形とは言え、一種の知的エリートであるバノンの方が敵視という形での敬意(脅威)にふさわしいということなのかもしれない。
Reflections on the Revolution in Europe Immigration, Islam, and the Westという著書のあるChristopher Caldwellのバノンは何がしたいのかという内容のコラムが読み応えがあった。
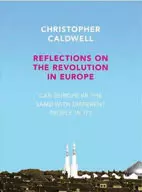
https://www.ft.com/content/106c266a-35dd-11de-a997-00144feabdc0
差別主義者、反イスラム、女性蔑視という今外部からのレッテル貼りだけではバノン氏を突き動かすものが何かを決して理解できない。彼が今標榜する政治的イシューが何かではなく、彼は一体どんな人間なのかということを知ることの方が、バノンを巡る懸念を直視する上では重要だと主張している。
彼の履歴にも若干触れた面白いコラムだった。
What Does Steve Bannon Want?
スティーブ・バノンは何がしたいのか
https://www.nytimes.com/2017/02/25/opinion/what-does-steve-bannon-want.html
(以下意訳。厳密性に保証なし)
政治というものを体系的なイデオロギーという観点から見ようとする人にとってはトランプ大統領は厄介である。彼は、自分のアジェンダを体系的に説明しようという傾向がないというか、できないからだ。
このためスティーブン・バノン首席戦略官がやり玉にあがることになる。
理由は、彼が、体系的に物事を考える才能があると思われているからだろう。反トランプ陣営はバノン氏を政敵として見るだけではなく、トランプ氏の考えていることを探る探針としての役割も期待しているのだ。
トランプ主義などいうものはおそらく存在しない。我々がぎりぎり理解できそうなのは、バノン主義とでもいうべきメッセージ群なのだ。
バノン氏(63歳)は彼の異端の履歴、すなわち海軍将校、ゴールマンザックスのM&Aスペシャリスト、エンタテインメント業界の投資家、ドキュメンタリーの脚本家、監督、ブライバートニュースにおける有能なサイバーアジテーター、そしてトランプ氏の大統領選挙におけるCEOというすべての職歴において、凄まじい知力を見せつけてきた。
ハーバードビジネススクール時代のクラスメートは、ボストングローブの取材に答えて、「クラスの中でトップ3の知力を持ち、おそらくはもっとも賢かった」と答えた。
ローマカトリックの組織である人間の尊厳教会(The Institute for Human Dignity)のBenjamin Harnwellは、彼を「歩く参考文献リスト」と読んだ。
バノン氏は保守主義に関しては遅咲きで、政治に全力を投入したのは、911の攻撃以後だ。そのため、自分の同世代の保守主義者たちが遠い昔に失くした情熱で保守思想に取り組んでいるようだ。
トランプ政権入りして1か月で、バノン氏はその影響力を証明した。大統領の就任演説の草稿作成を支援し、米国家安全保障会議の中の重責を獲得し、現在、据え置きになっているものの、ムスリムの影響の大きい7か国からの入国禁止令の主唱者であると報じられている。トランプ政権はムスリム同胞団をテロ組織として取り扱っているという報道がなされた。これは、バノン氏自身が、脚本家、トークラジオのホストとして長年にわたって主張してきた考え方を反映している。
外部からのコメントは皆、バノン氏を、コミックの敵役の悪漢、インターネットの悪魔、偏見の塊、反ユダヤ主義、女性蔑視、隠れファシストとみなしている。元下院議長(House Speaker)のナンシー・ペロシとニューヨーク州民主党議員のJerrold Nadlerは、バノンを白人至上主義者とまで呼ぶ。彼の強硬な保守派、厄介な過激派を示す証拠が、多数メッセージとして発信され、誤読され、炎上している。
バノン氏に対する懸念に十分な理由があるのは当然だ。しかしこういた懸念には的外れなところがある。バノン氏が20世紀のイタリアの過激派Julius Evolaのことをたまたま知っていたからということでファシズムとみなすことができるわけではない。
バノン氏がブライトバートを、「オルトライトのためのプラットフォーム」と言ったからといって、彼が差別主義者だというわけでもない。オルトライトというのは、特定の白人至上主義者だけではなく、より広い種類の過激派に対して適用される広く、しかも、不正確な用語なのである。
バノン氏が保守派の大会であるCPACの2013年と2014年の大会に、どちらかと言えば、敵対的といえる、招かれざる客というパネルのホスト役になったからといって、小物的印象を与えたわけではなく、むしろイデオロギー上の黒幕感を漂わせたという方が正しいようだ。
バノン氏のパネルには、主流派の、元議会議長のNewt Gingrichやブッシュ政権の元司法長官のMichael Mukaseyなどが参加しており、軍事的準備、リビアのベンガジでの米国の派遣団への2012年の攻撃等が共和党がこだわる馴染み深い論点を議論した。しかしある意味、Foxニュースを見ているのとさほど変わりはなかったともいえる。
バノン氏が最近の共和党主流派と大きく方向性が違うのは、彼の包括的なナショナリズムにある。
彼は国家主権、経済的ナショナリズムの賞揚、グローバル化への異議申し立ては、英国のEU離脱派や多国籍主義のEUに敵対するグループと共通の土俵に立っている。
木曜日に開催された今年のCPACで、「米国はボーダレスな世界における単なる経済単位以上のものである」がトランプ政権の政治哲学の中核であると宣言した。曰く、米国は単一の文化と存在理由を持つ国民国家(Nation)なのだ。
バノン氏のイデオロギーの源の一つは、トランプ氏人気と同様に、グローバル経済に対する国民の絶望の中にある。
曖昧なトランプ氏とは違って、バノン氏には、アメリカの国家主権がどのように敗北し、それについてどうすればいいのかについての、詳細な私見があり、外部に対してしっかりと説明ができるのだ。
この点については、Tea Partyの活動家と考えを共有している。規制を実行する政府官僚がアメリカ国民固有の民主主義的特権を奪っているという考えだ。この官僚階級が今や官僚国家を公正し、自分自身の力をさらに増し、仲間の資本家たちの懐を温かくさせているというのが彼の考え方である。
バノン氏が木曜日に、会場内で、官僚国家(administrative state)の解体を宣言した。外部者からはたわごとに聴こえたかもしれないが、参加者にとっては会場全体に、高い電流が流れる強烈な、信仰告白として響いたのである。一連のノスタルジックな嘆きや不平不満に陥っていた保守主義を、トランプ主義の下で、実行性のあるプログラムへと全面的に作り替える改修工事の責任者がバノン氏なのだ。
バノン氏は、Tea Party的レシピに、彼固有のパーソナルでユニークな隠し味を付け加えている。彼の考え方のベースにはシンプルで、優美というか、ある意味、危険なほど単純化されている、歴史的サイクル理論がある。
これは1990年代にWilliam StraussとNeil Howeによって組み立てられたモデルである。それによれば、80年から100年のサイクルが、約20年間の高度期、覚醒期、解体期、危機に分かれて繰り返されるというものである。
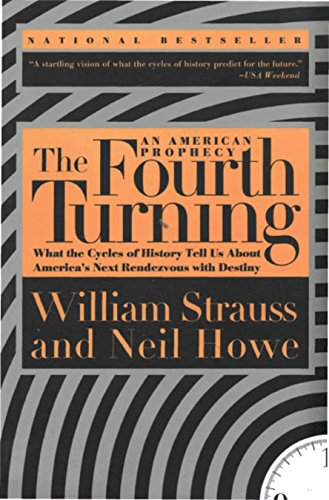
アメリカ革命、南北戦争、ニューディール、第二次世界大戦の後、我々は現在、もう一つの危機に直面しているのがバノン氏の長年の主張である。
2010年に発表された、彼の2008年の金融崩壊についてのドキュメンタリー、Generation0は、Strauss-Howeモデルを使って、何が起こったのかを解明している。Howe氏自身も、ドキュメンタリーの中で「歴史には季節変動があり、もうすぐ冬がやってくる。」と結論づけている。
バノン氏の見解は、過去10数年における保守主義の変化を反映している。
彼はこの変化を追いかけるためにその後も、映画を撮り続けた。2004年のドキュメンタリー、“In the face of evil”は共和党の英雄ロナルド・レーガンに対するオーソドックスな賛辞である。しかしその5年後の “Generation 0”は, それ以外のものも混じりあった奇妙な混合物となっている。
金融崩壊に対する彼の分析も単純ではない。映画の中で、当然、大きな政府に対して苛立つシンクタンクのサプライサイダーの論客や自由市場主義者とのインタビューが行われている。ただ、対象はそれだけにとどまらない。それに加えて、新しく、正統的とは言えない、保護主義的ニュースキャスターのLou Dobbsや投資運用マネジャーのBarry Ritholtzの意見もさらりと取り上げられていた。彼らは、自由市場が本当に、すべて自由かどうかを疑問視している。Ritholtz氏は、金融危機の帰結は、「富裕層に対する社会主義で、それ以外の万人にとっての資本主義」が行われたと主張している。
2014年頃にはバノン氏自身のイデオロギーの中心に、この不信感が置かれることになった。Institute for Human Dignityの開いた対談で、彼自身の資本主義に対する考え方を述べている。
「資本主義について考えてみよう。2008年の危機に関連して訴追された銀行の経営者は一人もいない。」彼はアイン・ランドやリバタリアン資本主義の客観主義派に対しても批判している。彼らの考えでは、「資本主義は、人々を商品とみなし、人を物的なものとしてとらえられている」。資本主義は、そうではなく、ユダヤ・キリスト教的基礎の元に築かれなければならないのだと。
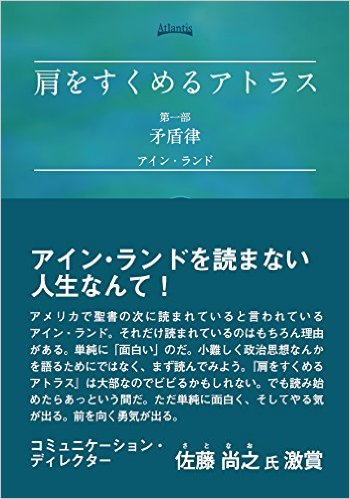
バノン氏の言い分が正しいとすれば、共和党にとっては少々まずいことになる。
バノン氏の発言までは、アイン・ランド型の資本主義は、レーガン時代のアジェンダの名残だった。自由市場的思考は、共和党を丸ごと呑み込みつつある。にもかかわらず、そこにユダヤ・キリスト教への没頭(一つの文化のある国家、国家の存在理由などの考え方)が、加わるのである。その上、共和党に巨額の政治献金を拠出した人々の望むのはビジネス志向の姿勢なのである。
しかしこういった姿勢に対して有権者は決して寛容ではないだろう。共和党において、雇用とコミュニティを、利益に優先させた最初の大統領候補は、1992年のパット・ブキャナンである。当時は、これが社会に対するよりよいビジョンなのか、単なる反動主義者の不平不満なのかを巡って、共和党内がもめにもめることになった。ブキャナン氏がこの論争に勝利するのに一世代かかったと言える。
2016年になると、以前は正気の沙汰ではないと片づけられていた貿易と移民に関するブキャナン氏の考え方が、急速に広まり、共和党全員が認めるまでになっていた。これを拒否したのは、既存の官僚群と、エスタブリッシュメント寄りの大統領候補だけだった。
ユダヤ・キリスト教文化とは何かを、バノン氏はあまり詳細に説明していない。しかし一つだけ明らかなことがある。イスラムがこれに該当しないということだ。バノン氏は、イスラム主義(Islamism)という過激派政治運動が危険な敵であるという認識を大多数のアメリカ人と共有している。彼の考え方がさらに論争を呼ぶのは、この政治運動がイスラム地域で発生して以来、宗教としてのイスラムの存在が大きくなり、アメリカの本来持つべき国家的権威を脅かしているという考え方である。これは、ジョージWブッシュ、オバマ両大統領ともに拒否してきた考え方である。
バノン氏のこういった見解は、決してバランスが取れているとは言えないが、徹底した多読に由来していることは明らかである。彼が熟読した思想家たちは、冷静で、対象から一定の距離を置くタイプというよりは、かなり熱狂的で、論争的な人々だった。
例えば、国務省は、事実上、イスラム至上主義者によって運営されていると主張したグランドゼロモスク反対運動を主導する扇動家のPamela Geller、彼女とも時折共同戦線を張る、Robert Spencer(Jihad Watchというウェブサイトの運営者)などが含まれる。
GellerとSpencerは、米国のイスラム化阻止という名前の組織のリーダーである。
さらに元国家安全保障省の役人だった、Philip Haney. 彼は、オバマ政権の管路湯たちが、政治的公正性(Political correctness)というイデオロギーを厳守することで、一般市民の安全を危うくしたと批判している。
トランプ大統領は、インテリの間で不人気なので、彼の政権を支える思想家たちは、みなある意味で、非妥協主義者、反抗者、個人主義者の集まりになっている。これまでのところこのことが米国にとって意味のあるものとはなってはいない。
間違いなく、ワシントンはバノン氏にとって敵対的な環境となった。ワシントンの政策テクノクラートは、バノン氏が乱入し、簒奪した政権に職を得ようとすると、多くの間違いを呑み込み、信念を大幅に曲げるというような高いコストを支払わねばならないことになっている。
トランプ大統領も人気投票で過半数を占めることができずにいる。エスタブリッシュメント側の保守派も、自分たちの嫉妬心を、バノン氏が人付き合いが悪く、危険であると考えるのが節操のあることであると取り違える傾向がある。
彼は本当にそういう人物なのだろうか。昨年、歴史家のRonald Radoshが、後にバノン氏は否定したものの、数年前のバノン氏の以下のような発言を紹介して、彼のイメージ作りに多いに貢献した。曰く、「自分はレーニン主義者であり、あらゆるものを破壊する」である。
1990年代の初めからバノン氏と共同で脚本作成を行ってきたJulia Jonesによれば、「バノン氏のイデオロギーだけでは、彼を突き動かすものすべてを捉えることはできない」と言う。15年近く、共同で脚本を作成してきた彼女は、そのキャリアの方向性が一貫しているとは言えないバノン氏が長く働いたことのある数少ないパートナーである。
彼の世界観を理解するための鍵は、兵役にあるという。「彼は兵役というものに高い敬意を持っている。」さらに「彼はダルマという言葉をよく使う」のだという。出典はバガバットギータだったと彼女は記憶している。ダルマは、人生において辿る道、あるいは宇宙における自分の居場所を説明する概念だ。
ハリウッドに来た当時のバノン氏はあまり政治的ではなかった。2年間で、二人は26回のテレビシリーズを製作した。自己の秘密を探る人々というテーマで、対象は、コナン・ドイル、ニーチェ、マダムBlavatsky, ラーマクリシュナ、Baal Shem Tov, ジェロニモと、多岐にわたった。一種の人間のコレクション作りのような番組作りだったという。
911のテロ攻撃が、彼を変えた。その後、政治に一気にのめり込む中で、ハリウッドにおける二人のパートナーシップは終了したという。彼の作る映画の「プロパガンダ的トーンが私には少々攻撃的すぎるように思えたから」だという。
ジョーンズ女史は文学的で、政治においてはリベラル左派に属する。彼女は、バノン氏が「ナショナリズムの中に自分の居場所を見つけたことを」残念に思っている。しかし、彼女曰く、彼はアナキストでも、差別主義者でもない。
バノン氏のイデオロギーの部分にフォーカスしている人々は全くの的外れである。バノン氏に対する懸念にはもっともな理由があることは認めよう。
しかし懸念すべきは、様々な論点に関して彼がどのような立場にあるかということよりも、彼がどんな人間かということの方だと思われる。
彼は政治権力の世界では新参者である。実際、政治に関心を持ったのも比較的最近のことなのである。彼は、権威を破りたいと考えている。前世紀の遺物と化したイデオロギーのどれも肯定はしないが、歴史のサイクルという考え方には親近感を感じていて、丁寧に言えば、未だその有効性が試されていないと考えている。
より重々しく言えば、彼は、グランドセオリーによって刺激を受ける政治におけるインテリなのだ。そしてこれまでの予測不能な結果を生みだしてきたのが、この組み合わせなのである
( He is an intellectual in politics excited by grand theories- a combination that has produced unpredictable resulMost ominously, he is an intellectual in politics excited by grand theories- a combination that has produced unpredictable results before.)
この組み合わせがこれから何を生み出すのだろうか。
バラク・オバマも同じような形で、歴史の方向性や円弧(arc)について言及していた。
バノン氏の見解の循環性に内在する緩和的要素を期待するものもいるかもしれない。歴史が概ね線形であると信ずる進歩主義者は、政治に関わると不死性を巡る聖戦を戦いだしかねない。歴史は循環的であると考える保守派は、今後の20年か80年ぐらいの期間をなんとかすることに集中する。彼らの任務もその意味で、他の仕事と同様に未了が前提なのである。(以上)